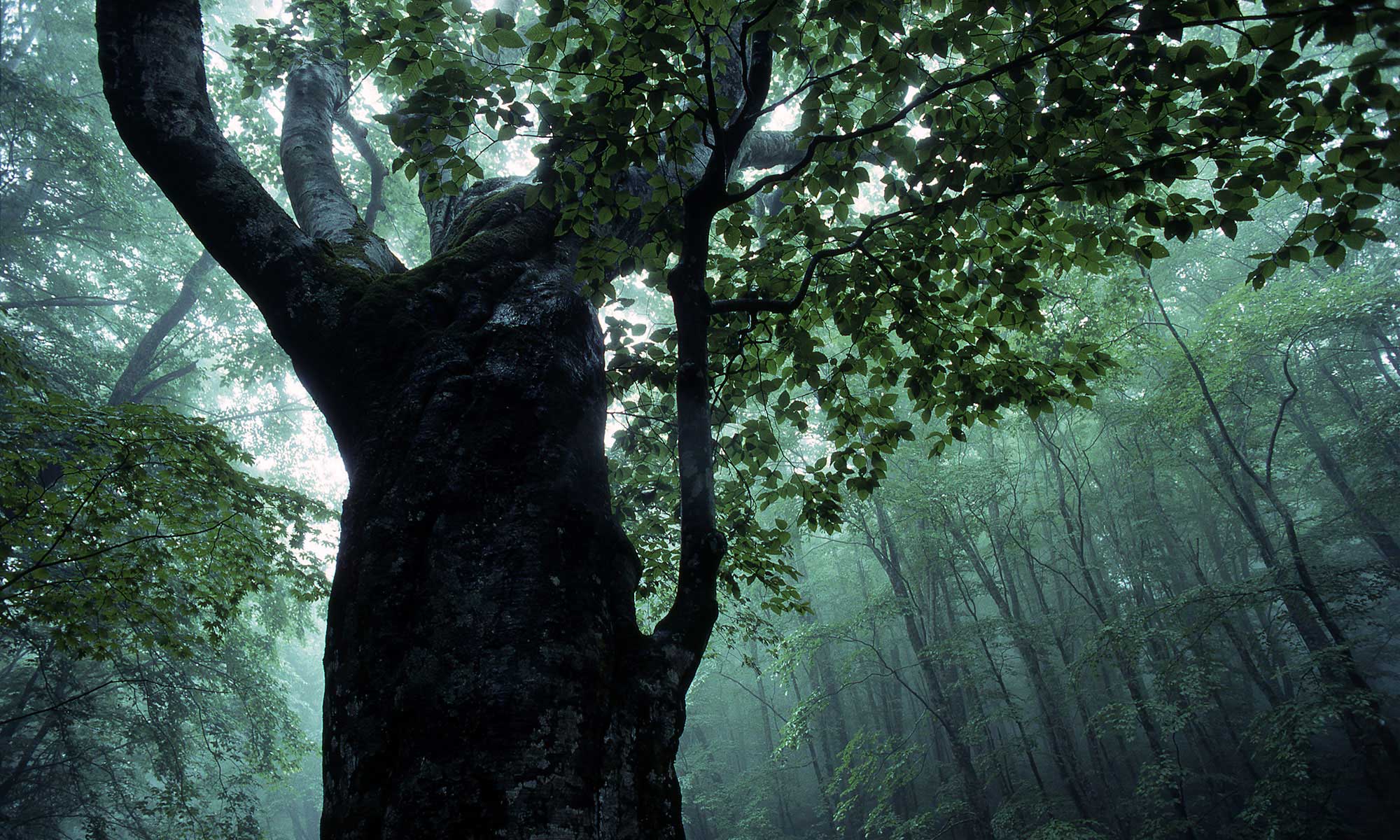震災後しばらくしてから、岩手県の漁港・大槌町の被災地で「刺し子」が女性たちの助けになっていると聞きました。ですが、刺し子という手仕事が港町である大槌町に伝え残っている認識がなかった私は、すぐ現地に問い合わせました。それは、復興の取り組みの一つで支援団体が現地の避難所で被災者の方たちに提案した活動だったことを知りました。
「刺し子」とは東北に古くから伝わる代表的な工芸のひとつで、北国の厳しい気候風土を生き抜くために生み出されました。麻しか身につけられなかった庶民は、温かく丈夫にと麻地に貴重な木綿糸を埋めるように刺し、一枚も捨てられない端切れは積み重ねるようにして糸を刺し込みました。まるで、命があるかのように大切に布を使い尽くした、かつての北国の女性たちの暮らしの知恵です。
大槌町で作っているという刺し子の作品・コースターやふきんは、写真で見るかぎりではごくごく簡単な作りで、元来の「刺し子」とは言えないものでしたが、今に伝え残る刺し子が被災地の方たちにとってどのようなものなのか、どんな風に受け入れられているのか、無性に知りたくなり、9月初めに大槌町へ向いました。
沿岸を走る国道45号線の景色は以前とは違っていました。何も無くなってしまった場所に片づけられた瓦礫が山になり、その周りに雑草が生え始めていました。そのやわらかい新しい緑が広がっている光景は今でも頭から離れません。
時は流れるということ、こんなところにも命は芽吹くということに、受けた被害を思うと自然の前の人間のちっぽけさとその無常観に沈み込みそうになりました。けれども車窓を通り過ぎる景色を見ながら思いました。あの草は、「私たちのように少しずつでも前へ…」と言っているのかもしれないと…。
大槌町に着いて驚きました。その記憶の町は、全て無くなっていました。まるでSF映画で見る別の星に来たような錯覚を覚えました。かろうじて残る道路と山の方向を確かめながらやっと土地勘を保てるといったあの感覚は、初めての経験でした。
その中で、刺し子の活動をしている支援団体の吉野さんと会うことが叶いました。待ち合わせた、たった1件の仮設のコンビニは、まさに町のステーションになっていました。車がたくさん停まっていて人の出入りが常にあり、このコンビニを中心に、大槌町の人と人とを結ぶ数えきれないほどたくさんの線が、この場所で交わって走るように見えました。
吉野さんは両手で握手してくれ、刺し子をしている方々の住む仮設住宅へ向かう道すがら話をしてくれました。
「避難所では何もすることがない、今日をどう生きていいかわからなくなっていたんです。その女性たちに、まず誰でもできるもの、どこでもできるものをと考えて「刺し子」を思いついたんです。とにかく今日を生きることでしたから。」
とはいえ、針も糸も布もない。そんな中で刺し子をするためのコースターやふきんを、“キット”にして揃えたと聞いて、この支援活動への強い熱意を感じました。1枚仕上げるごとに、手間賃としてコースター300円、ふきん500円が、作り手に支払われるそうです。
「刺し子って言えるものではないんですけど…初めは2~3人から、今は30人くらいでしょうか。刺し子と出会えて良かったと皆さんに言われています。」と言いました。
刺し子をしている中の一人で、一生懸命に取り組んでいるという小川さん(76歳)に会いに、仮設住宅を訪ねました。小川さんは家を流され、最愛の妹さんを亡くしていました。
家の前に到着し、小さな玄関から「小川さん」と声をかけると「どうぞどうぞ」という明るい声が聞こえてきました。家の中は仮設住宅とは思えない程大きく立派な家電が目立っていて小川さんの元気な声とこの風景に、被災地であることを一瞬忘れそうになりました。
しかし、こたつ越しに小川さんと顔を合わせて、そう思ってしまった自分を恥じることになりました。小川さんのダウンコートの襟の汚れ、気づけばこたつ掛けも薄く、有り合わせで凌いでいたからです。
そんな気持ちに戸惑いながら「本当に大変でしたね。」と声をかけると、「でも、この刺し子あるおかげで何とが元気でやっでいます。ほんとに助けられでます。」と小川さん。こたつの上にやりかけの大槌町のシンボルマークのカモメの絵が刺されたコースターが重なっていました。
「避難所には4ヶ月いました。ここさ移ったのは7月でした。いやぁ、それはもう、とにかく、手も足も伸ばして寝られるってのがほんとにありがだいど思いました。大の字――。その日は夏だったがらそのまま寝ました。
とにかく避難所は我慢しか無がった…。自分だけでない、みんなだもの…。
何とか食べるものも、着るものも足りてきた頃、男の人は瓦礫の片づけがらやらねばないごどいっぱいあった。でも女の人は何もするごどなくてなんだか毎日ただ息してるだけみだいな。
ただただ我慢するだけでとってもせづながった。でもあすこにいた人、皆だがら…。
家が無ぐなった、家族が死んだ、まだ行方不明…。私だけじゃない。そういう人はいっぱいいたんだ…、わがるんだよ。昼間はまだいい…、夜になればすすり泣くのも聞こえるし、身体を震わせでいる人もいだ…。」
避難所の暗闇に声を殺した苦しみや悲しみがどれだけ立ち込めていたかと思うと、恐ろしさに、胸がしめ付けられる思いでした。
「何かと不自由で大変だったけどみんなだから我慢するしかないんだよね。」小川さんは“みんなだから”と繰り返しました。
「この刺し子のこどは避難所で知りました。何やってるのかな、と最初見てましたけど、これだら私にもできるかなと思って。若いころ洋裁してましたから。」
刺し子をするようになってどうでしたか、と尋ねました。
「針と糸持って、少しずつ出来上がっていって。一枚が二枚になってまた刺して。そのうち夢中になって…。その時だけは忘れでるんだよね。最初は刺し子やればお金もらえるって知らないでやってだの…。」
そういってまたこたつの上のやりかけのコースターに針を進めていました。
被災地の刺し子の活動は、手を動かすことでもたらされる無心の境地が、深い苦悩にある人々の心を助けていたのではと感じた時でした。
小川さんは続けました。
「私、こうして助かったけど、妹は死んだんです。他のことはいい…。何が悔しいってそれが悔しい…。だっておかしいでしょう。死ぬのは年いった人からでしょう。」
小川さんは亡くなった妹さんと2人で40年近く大槌町で『七福』というやきとり屋を営んでいました。そして大変地元に愛されたお店だったそうです。小川さんの話から、妹さんは、苦楽を共に歩んできたかけがえのない大切な存在だったことが伝わってきました。
妹さんは、震災当日、開店の準備でお店にいて、逃げる途中で津波にさらわれてしまったのだそうです。
「探しました…。落ぢでだ棒拾って杖代わりに、帽子かぶってマスクかげで何日も何日も探しました…。なんぼ探しても見つからながったの。でもやっと見つがったの。明日が共同埋葬っていう日に…良がった…。」
「妹のことは“ヤッコ、ヤッコ”って呼んでました。やす子っていいますけど。ヤッコの墓は避難所から近かったですから、何回もお茶飲みに行きました。差し入れにもらったビール2本持って。さまざまなごど話しました。そして泣ぎました。墓の前で声出して泣ぎました。大きい声だして…。避難所では泣けないでしょう。」まるで妹さんの墓の前に座る小川さんが見えるようでした。
「私、見つけたんです…。」
何を?
「これ。」
取り出して見せてくれたものは、震災による火災で焼けただれたやきとり網の焦げ付きを取る小さな金属のヘラでした。
「ヤッコを探しているときに流された店の近くで見つけだの。これ、ヤッコのものだ!って思った。いや、違うがもしれません…。でもいいんです。これはヤッコのものなの。でも私、ついこないだまで、このごど誰にも黙って懐にしまっでだ。口に出してしまえばなんだか消えて無ぐなってしまいそうで…。」
そう信じたい気持ちが痛いほど伝わってきました。
触ってもいいですか?
「どうぞ」
全てが失われ、変わり果てた町で妹さんを探しながらお店のあった近くで拾ったこの金ベラ。このひとつの道具にどれだけの想いを重ねたかと思うと、胸が熱くなるのをこらえられませんでした。この金ベラに亡き妹さんを重ねて、そこにある小さなひとすじの光に身を寄せるように、小川さんは肌身離さず持っていたのだと思いました。そして、これまでの妹さんとの人生を肩代わりできるその道具の存在が本当にありがたく思えました。
その時、小川さんは言いました。
「私、“七福”やるって決めたんです…。もう1回やるって…。ヤッコのためにも。この刺し子で少しずつ貯めたお金も使わせてもらいます。」
既に小川さんは七福の再開に向かって準備を進めていました。
「実は私、足が悪ぐでちゃんと歩げながったんです…。津波も逃げるのにもやっとだったんですけど、不思議です。今、歩げるようになったんですよ。バイクさも乗って動き回ってます。」
前向きに進む小川さんの晴れ晴れとした顔からは、決意と張り合いが伝わってきました。
まるでヤッコ・妹さんがのりうつったように思えました。そしてこの時、大事にしまっていた金ベラを見せてくれたわけが判ったような気がしました。
悲しみや苦悩はその人になり変わらない限り、わかり得ることはないと私は思います。けれども、“人を想う”ことは、これほど人を支え、人を強くするのかと、小川さんを見つめながら実感しました。
「自分でもわがらないけど、ヤッコと七福のことを思えばなんでもできる…。だってそうでしょう、死んだと思えば。」その強い決意に、がんばりすぎる小川さんの身を案じないではいられませんでした。
76歳の小川さんの仮設住宅の一部屋は、新聞などで彼女のことを知った全国の人たちから、やきとり屋『七福』を再オープンするために支援として届けられた道具でいっぱいになっていました。
「たくさんの人から手紙をもらったり、ものを送ってもらったり、本当に涙が出ましたよ。その気持ちがとっても嬉しくて…。」
私は、鍋、ボール、徳利が整理されて重なる隅に、3本立っている一升瓶を見つけ、尋ねました。それは「七福」秘伝のやきとりのタレでした。小川さんと妹さんしか作ることができない味で、この仮設住宅で自ら仕込んだものだと教えてくれました。
匂いを嗅がせてもらうと本当に良い匂いがしました。このタレが焼けた香ばしい香りとその煙が立つのが、目に浮かぶようでした。仮設住宅の暮らしの中でも、こうして前へ、前へと進む小川さんを、ただただすごいと思いました。
帰り際、小さな位牌に気づき、たずねると笑って「ヤッコ観音です。」と。私も手を合わせたいとお願いしました。
12月21日、悲願のやきとり屋『七福』は開店したそうです。やきとりの煙の向こうに小川さんの笑顔が見えるようです。
大槌町で刺し子をする人は、避難所での2~3人から30人近くになり、現在では仮設住宅を含め避難している先も合わせて170人まで増えているそうです。
集会所に伺った際、集まって刺し子をする人たちの中に針を持つ手元のたどたどしい若い女性がいました。「こうしていると、無心になれるんです。刺し子がなかったら、今の自分はなかったかもしれません…。」と話してくれました。そして、「生きていることをありがたいと思う気持ちになりました」と。
集会所に集まる人たちの手元には、それぞれの人生とそれぞれの刺し子があるように見えました。
「針と糸を持って刺すことを繰り返していると、太いものが上から降りてきて自分が消えていくようだ。」という刺し子職人の言葉を思い出しました。そして、余命わずかと言われた病人が「ひと針、ひと針そこに糸が渡るのを見たとき、ああ、私は生きていると思った」という話がにわかに私の中に戻ってきました。刺し子が授けてくれる無心という喜び。ひと針ひと針、自分の存在を確かめていく時、心が静かになってどこからか感謝の気持ちが生まれてくるのではないでしょうか。そして、感謝の気持ちは気付かなかった、身の回りの小さな幸せを見えるようにしてくれる。些細なことかもしれませんが、こうしたことが生きる力を紡いでくれるのではないでしょうか。そして社会とつながっている、関わっていると感じることが生きる上での大きな支えになるのだと思いました。
涙ひとつ見せず「絆じゃなくて縁なの」と繰り返し言っていた小川さん流の言葉の意味がわかったような気がしました。深い悲しみと苦悩を抱えているけれど自ら足を踏み出すことで、そこに開けてくるものがある。それが「縁」。これは小川さんのこれまでの人生であり、これからの生き方を話してくれていたのだと。