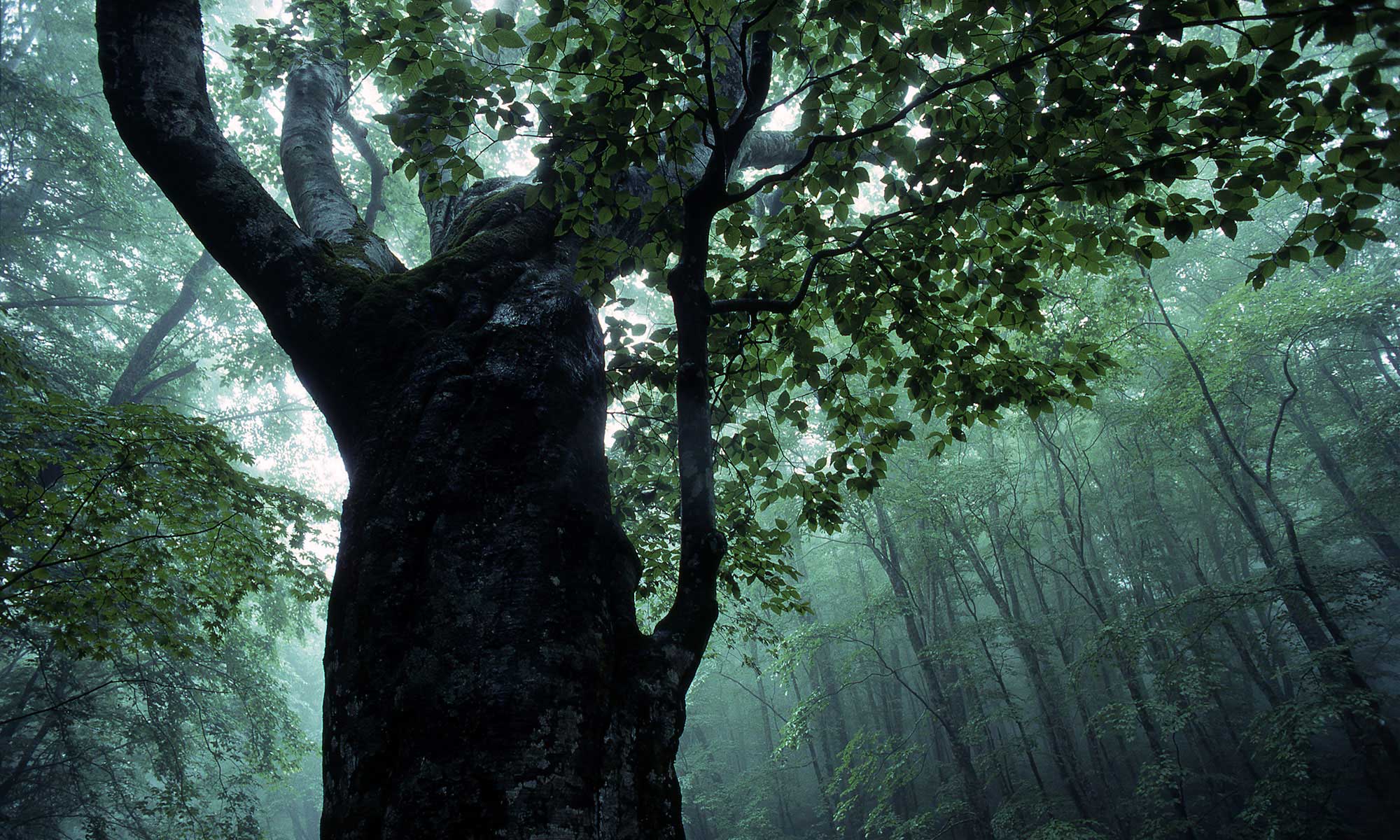南部鉄器といえば鉄瓶が筆頭に上がりますが、鉄瓶を引き上げるのに欠かせない“つるかじ”という仕事をご存じですか。鉄瓶の持ち手を作る技のことです。なくてはならない技なのに光の当たることはなくあまり知られていない手仕事、縁の下の仕事です。南部鉄器の産地、岩手県内でも携わる人はごくわずかしか存在しません。でもこれを、今の暮らしに使う方法はないのでしょうか。
つるかじの仕事
初めて彼の工一房を訪ねたときのことを思い出します。ここかな?と窓越しに中をのぞき、仕事中の柴田さんに声をかけました。初めて作り手を訪ねるときはいつも、顔を合わせる瞬間がいちばん緊張します。「こっちさどうぞ」と返事があり、仕事場を抜け、奥の炉のある部屋へ通されました。「まあ見ででください」。あいさつをすませると休めていた仕事を再開しました。何本か重ねであった鉄棒のうち1本を炉に入れ、真っ赤に焼けた鉄を物差しもなければ型もないなか、ただ勘だけを頼りに金槌でたたき続け、鉄瓶のつるの形にしていきます。丸みを帯びた鉄は再び炉の中に入れ、型が決まったら今度は熱い鉄を水に入れ、ジユツという音とともに、ひとつの仕事が終わるのです。
技の重み
仕事をする姿を、柴田さんから少し離れたところで見ていました。炉の赤々と燃える色、鉄をたたく音、自の前に立つ柴田さんの振りかざす手と体全体の力のある動きに無言で見入りました。柴田さんの息づかいが聞こえてくるようでした。たたかれ、次々と形をなしていくつるは、まるで型に入れて作ったかのように、まったく同じ形。驚きました。その瞬間、手の甲が熱くなりました。何?あわてて払いましたが手から火が吹き出すように制掛川く、タンパク質の焼ける臭いがしました。柴田さんが、危ないからここに、といってくださった椅子からいつのまにか立ち上がってかなりそばまで近づき、火の粉が飛んでいたのです。吸い寄せられるように見入っていました。柴田さんがたたき焼けた鉄粉が飛んだもの。熟練した技の前、私を気づかつてくれた柴田さんに知られたくなくて、あわてて右手を隠し、何もなかったかのようにふるまいました。人の生み出す技の素晴らしさを心の底から思い知らされました。
病
その年の秋、私は過労から耳に異常を感じるようになり、盛岡の病院に入院しました。十和田湖から自宅前まで戻ったにもかかわらず、車の運転席に座ったまま眠り込んでしまうほどの激しい疲労感は、その知らせだったのかもしれません。左の耳にエンジンのような大きな音が鳴り続け、ある朝、顔の左半分が動かず、表情が作れなくなっているのに気づきました。検査をしても何の病気かわからず、耳における最悪の病気だと診断されました。あとで知つたのですが、家族は、もうだめかもしれないと覚倍していたようです。面会謝絶の個室でらちが明かない自分の状態をどう受け止めてよいのか。どうしていいかわからずベッドに横たわり、窓の外ばかり見ていました。もしかすると私はここまでか、ならばゆずりはも:::。すべてのことが私から去っていました。折しも年明けに、第回目の「ゆずりは東京展」を控えているのに:::。
“あいさつ”の本当の意味
背中で「田中さん」と呼ぶ声がしました。振り返ると、柴田さんの顔が大きく目に飛び込んできました。面会謝絶なのに、なぜ?「遅くなりました。お加減はいかがですか」。直立不動で、まるで敬礼するかのよう。どうして、おつきあいをしてまだ半年ほどなのにたくさん買わせていただいているとはいえないのに、娘ほど若い私にこうまでしてくださるのでしょうか。ほんの数分。お話をし、病室のドアまで見送り「ありがとうございました。どうか今後ともよろしくお願いします」と、頭を下げたとき:::。私がいました。そういった言葉と自分のお辞儀をした体の動きがスロlモiシヨンのように頭によみがえります。私の中に“ゆずりは”が戻ってきました。私には、ゆずりはがある。あいさつとは、背筋を伸ばして相手を見る、頭を垂れ、目を伏せ、心を込める。そこでひと息っき頭を上げる。その一連の動きにどれほどの心を込められるかが大切なのです。あいさつが、すべてを変えてくれます、私のように。その日から私の病室はオフィスになりました。食事をするベッドの上の板は机になり、ノートとペンを置いて作り手とやりとり。電話で様子をうかがい、病室に打ち合わせに来る方もいました。やがて、今では非常に珍しい病気、結核性中耳炎であることが判明しました。
心から感謝しています
それから何年かたち、柴田さんと連絡がとれなくなりました。工房の電話はつながらず不安になり、他の作家さんからご自宅の連絡先を伺つてなんとか話をすることができました。「もう年だ。そろそろ仕事をやめてもいいころだと思う」。柴田さんが仕事をやめたことを知りました。でも私は納得がいきませんでした。柴田さんの仕事に打ち込む姿からは、何かがあったとしか考えられません。でも容易にはご本人も奥さまも話してはくださいませんでした。もう柴田さんの仕事が見られない::。そのことが無性に淋しかった。糖尿病に併発してがんを患い、自ら廃業を決断したと知ったのは、何か月かたってからのことでした。「いちばん悔しいのは、あの人だったと思います。やっと初めての工房を持てたのに:::」。病名は告げず、私にもらした奥さまの言葉が心に染みました。その後「仕事はされていなくてもお会いしたい」と度々連絡をとりましたが、その願いはかないませんでした。結局、私の病室でお会いしたのが最後。あらためて電話をかけたときには、かなり容体が悪くなっていました。奥さまが病床の柴田さんに取り次いでくださり「私、もうだめです:::」とか細くかすれた声が、今も耳について離れません。一度柴田さんを訪ねたことがありました。ですが運悪く柴田さんはお留守。あのとき無理にでもお会いしておけばよかった。その数か月後、柴田さんは亡くなりました。私は、柴田さんに心から感謝しています。私にゆずりはを呼び覚ましてくださった大切な恩人。せめてお礼をちゃんとお伝えしたかった。「もうだめです:::」という柴田さんの手を握りしめたかった。ありがとうございます、柴田さん。

馬?
柴田つる工房はお弟子さんの田中-一三夫さんが引き継がれています。初めて訪れたとき柴田さんのそばで仕事をしていた方です。生前、柴田さんに「つるかじで馬を作ってほしい」とお願いしたことがあります。昔、南部地方の暮らしで大切な役割を果たしてきた馬。その馬は今も私のそばにあります。最近そのことを思い出し、あらためて田中さんにお願いしました。すると「あれ、親方が作ったのでねえ、オレが作ったのだった」。一瞬戸惑いましたが、今もなおρ親方と呼ぶ声に、不思議な安堵感を覚えました。「あの作り方はただくのに大変でできればやりたくねえんだよ」。大変さを惜しんではいけないとわかっていても、できない事情も知りました。目的はつるかじρという仕事を皆に知ってもらうこと。そして、つるかじで動物や自然界のものを表現することで、東北らしさを感じてもらい、人と自然のかかわりを考える機会になるよう願つてのこと。「田中さんがしやすい仕事でかまいません」やがて馬は鳥になり、ゆずりはに届きました。次は犬のような馬に。それでもかまいません。
親方
テレビで南部鉄器が特集され、ゆずりはがお世話になっている老舗が登場することを田中さんから聞きました。見てみるととてもいい番組で、田中さんが出演しているではありませんか、画面いっぱいに。そんなことはひと言もいわず、あくまで他所に花を持たせるような話し方だったのに。そんな田中さんが急にとても素敵に思えました。柴田さんを親方と呼ぶ田中さん。“親方”という響きがとても好きです。子弟関係を考えたとき、「よぐ見て取れ」とよくいわれます。知識として本で教わるわけでなく、本当に学びたければ見て取れ、という意味でしょう。長い時聞を一緒に過ごすことで技だけでなく、考え方や生き方、人間性をも感じ、学び取っていった人聞が“親方”という呼び方をするのではないでしょうか。残念ながら、今の世の中ではそれが薄くなっています。技(知識)が本当に血となり肉となるのは、親方(親)と時聞を過ごし、わからないながらも時聞を過ごすことで感じ取る力を養い、育てることではないでしょうか。「柴田さんと似ていますね」と田中さんにいいました。「そうですかあ」と照れくさそう。今度は田中さんらしいつるかじを、多くの人に知ってほしいと思います。